こんにちは、ティナです!
そろそろマイホームがほしいと思った私たち夫婦が向かった先は、BESSの住宅展示場「ログウェイ」でした。
ぼんやりとしていた家への気持ちが、モデルハウスを見学することで現実味を帯び、先日とうとうBESSさんに、
「来年春までには家を建てたい!」
という意思表示をしてきてしまいました!
どうしよう…。
歯車が動き出してしまった…。
どうしよう。

とりあえず落ち着かなきゃ。
なお、この記事は「マイホームの記録」となっており、実は今回が第4回目。
第1回目から読んでみたい人は下のボタンからどうぞ。
前記事「Gログなつ・セッカY」が気になる方は以下のボタンをクリック!
第4回目のテーマである「ワンダーデバイス」に興味のある方はこのまま読み進めてくださいね!
Contents
【BESS】ワンダーデバイス・フランク7の特徴

BESSのログウェイ(展示場)でひときわハイセンスな外観を持った「ワンダーデバイス」。
この建物を前にすると、
「家を選ぶのは果たして人なのか?」
「あるいは家が人を選ぶのではないか?」
…なんて、どこかのパンフレットに載っていそうなキザな文句が出てきてしまいそう。
でも、なんとなく分かる気がしませんか?
まあ、深くは語りませんけどね…。
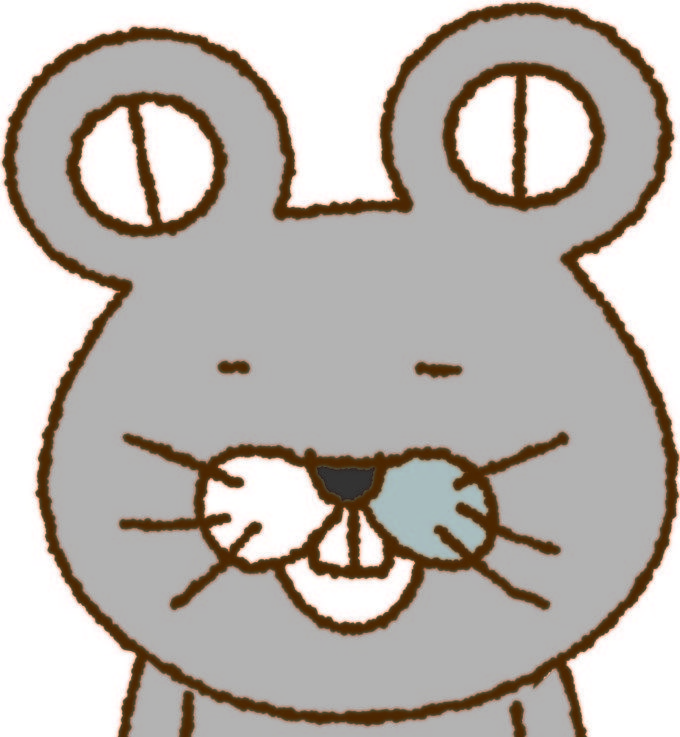
ハイセンスな家にはハイセンスな住人が…

ねずみ、みなまで言うな!
では、さっそくワンダーデバイスに潜入してみましょう。
BESS仙台にあるのは「フランク7」というモデルになっています。
BESSの家の特徴は、なんといっても広いデッキ。
ワンダーデバイスにも楽しそうなデッキがありました。

私だけでしょうか?
ここに横たわってひなたぼっこをするシェットランドシープドッグが見えますよ!
あれ、壁の向こうには飼い猫も。

早くお散歩行こうよ! 
お日さま暖かくて幸せ♡
…と、冗談はさておき。
屋根に取り付けたフロートシェードやハンモックチェアーがなんともオシャレですね。
子供たちも一目散にハンモックチェアーに群がっていました。

明かり取りの付いた茶色いドアを開けて中に入ってみると…

すぐに目に飛び込んでくるのは、硬質な印象のスチール階段。
「フランク」の遊び心の1つとも言えるこのオシャレ階段の下には、薪ストーブが設置されていました。

そして、この薪ストーブ(オプション)の前にはソファが置いてあります。
じんわりとした暖かさを堪能しながら、まったりとした時の流れを感じる…。幸せが滲み出てきそうですね。

この空間にテレビなんていらない!
テレビなんて本当に必要ない!
テレビを捨てよう!
でも一応、知りたい。
この配置だとテレビはどこに置くのがベストなのか…。
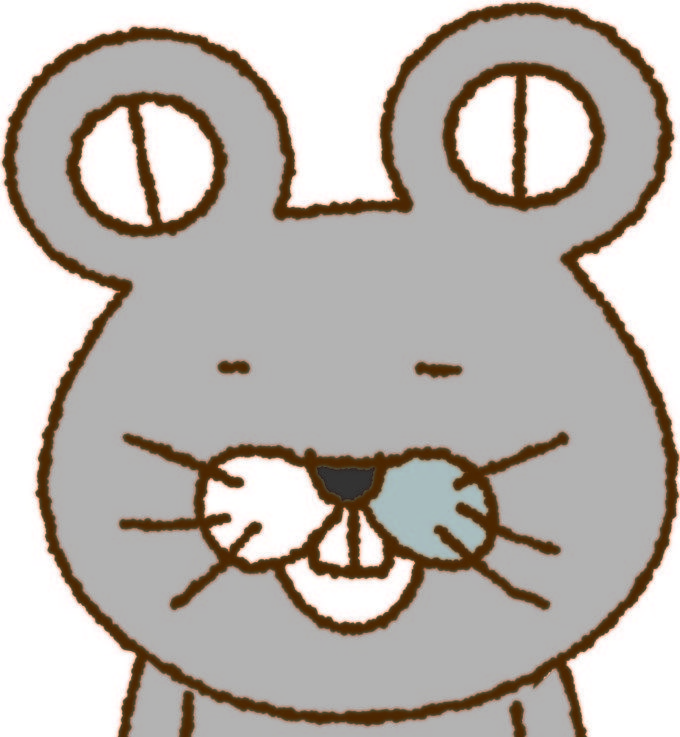
野暮な疑問はお捨て。
玄関を入って左手側にはアイランドキッチンがあります。
OSB仕上げがシックでスマートな印象を強調しています。
配向性ストランドボード の略。木片を接着剤と混ぜて熱圧成型した合板。

「あれ、このキッチン未完成?クロス貼り忘れたのかな?」って思ってた時期もあったっけ…。
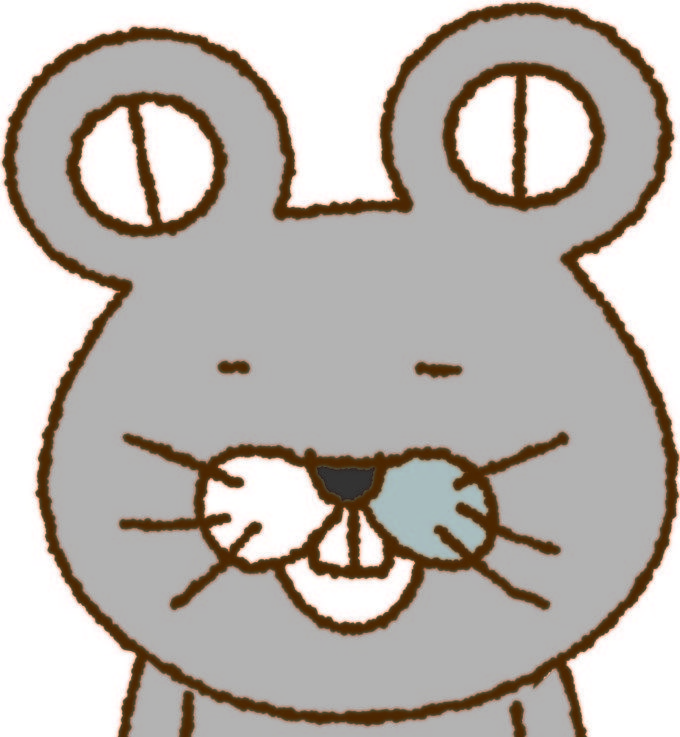
オシャレ上級者には程遠いね…
壁に設置された取り付け棚は丸見え状態なので、使う家電や食器類には気を遣いそうです。

ここはディスプレイ目的で使うことが大前提ですね。
色も形も材質も違うタッパーを重ね置いたり、大きさもまちまちなお皿を重ねてしまったら、その時点で生活感丸出し。
ちょっと高めのティーカップセットや、いつ使うの?!とツッコミを入れたくなるようなデザートグラスを並べておくのが正解かな(^^;)
シンクも広々。

ガスではなくIHクッキングヒーターなので、お掃除の手間もあまりかかりませんね。
換気口の剥き出し感が、またなんともいえません。

「壁の中を通して隠してしまう?そんなの時代遅れ」とでも言いたげな、この存在感。
敢えてなのか、それとも設計上ここを通す以外になかったのか。
いずれにせよ、「かっこいい」「いかしてる」と思い込めば不思議とそう感じられてくるから面白いですね。

ワンダーデバイスの水回りは、他のベスの建物にくらべ比較的スーペースを広く取っている感じがしました。

日差しの差し込むトイレ 
フルユニットバス
ただ、造り的にお風呂場とトイレが同じ空間にあるので、来客にトイレを貸す場合は神経遣ってしまいますね。
せっかくリビングをきれいにしていても、洗濯機とか歯ブラシといった生活感を見せざるを得ないのでは、なんだか虚しい気が…。
せめてトイレだけは別の場所に…ですかね。
1階部分はこれで終わりかと思っていたのですが、BESSからもらったパンフレットを見ると、ワンダーデバイス・フランク7には、1階に3.5畳のフリールームがあります。
ちょうどソファの裏手、トイレに隣接した場所です。

しかし、手元にある画像を見る限り、ソファの後ろには正方形の鏡が付いているだけで入り口らしきものは見当たりません。
どうやら、仙台のワンダーデバイスはフリールームがないパターンのようです。
パンフレットにも、
「多雪地では一部プランが異なります。」
と書いてあるので、仙台バージョンは多雪地に入るのでしょう。(多分)
ワンダーデバイスの2階は開放感がある
続いては2階です。
ワンダーデバイスの特徴的なスチール階段を上って行きますよ~。

登り切った所も決して狭すぎず。

ただ、スチール格子の幅が広いので、子供が身を乗り出したりしないかと不安になってしまいます。
オープンさのみを重視するのであれば、これ以上ない開放感ではあるんですけどね。

子供が小さいうちは開放感より安心感に重点を置きたいかも…。
階段を上りきると、そこには10畳の広いロフトがあります。


仙台ログウェイでは第二のリビングとしてテレビとソファが置いてありました。

子供の遊び場にしてもいいし、成長してきたら壁に面して机を配置し、学習ルームのような使い方をするのもいいかもしれません。

思いきって私専用のスペースにしちゃうとか!
そして、窓を開けると広々としたベランダ。
GログのNIDOにはかなわないけれど、これだけのスペースがあったら申し分ないんじゃないかな。

窓スペースも広いので、自然光も入りやすく、ついついまどろんでしまいそうです。
子供が大きくなるまでは、イスを置いてのひなたぼっこもお預けかな…。

だって、絶対イスの上に立って手摺りから身を乗り出すもの。
ベランダとロフトに接した吹き抜け空間には、グレーチング棚を設置することもできます。

隠さずに、あえて見せるディスプレイスペースらしく、配置する人のセンスが試される場所とも言えますね。
確認するのを忘れてしまったのですが、配置する場合はベランダに出て、外側から窓を開けるのでしょうか…。
っていうか、そもそもこの部分の窓の鍵はどうやって閉めるのだろう…。
写真を見た感じだと、鍵らしきものは見当たらないので、こちらの窓は固定で開かない仕様になっているのでしょうか?
ちょっとした謎が残ってしまいました。
なお、また展示場に行く機会があったら確認してきます!
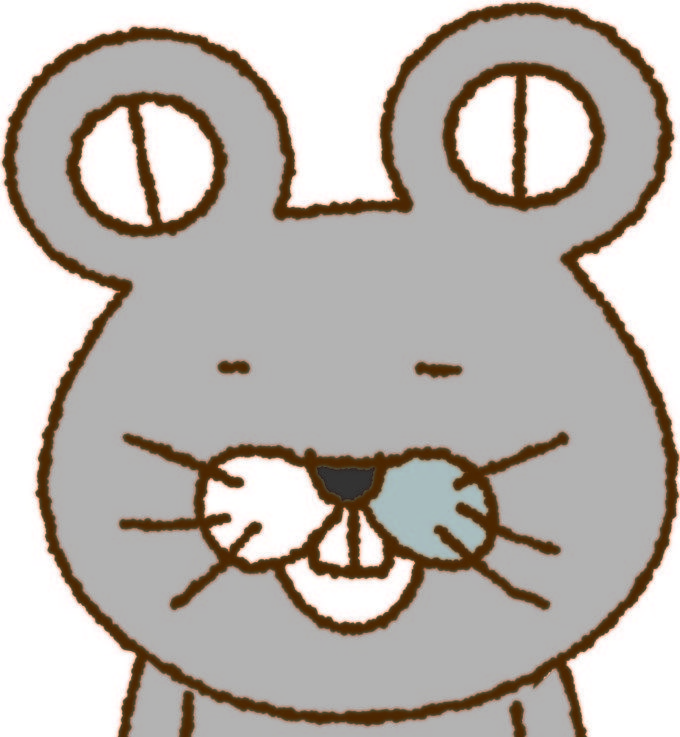
詰めが甘いね…。
追記:確認してきたところ、鍵は付いていませんでした。おそらく、手摺り部分を乗り越えて…ということだと思います。
グレーチング棚を始め、フロートシェードや蜘蛛の巣スイングなど、暮らしにインパクトを与えるガジェットは、BESSユーザーやログウエイクラブの会員になることで手に入れることができます。
※我が家もログウェイクラブ会員になりました!

階段部分から1階と2階を見渡せるという経験は、通常の家ではなかなか体感することができないんじゃないでしょうか?

1階で子供達が遊び、2階で夫がテレビを見ている。そしてそれを階段からジッと見つめる私…
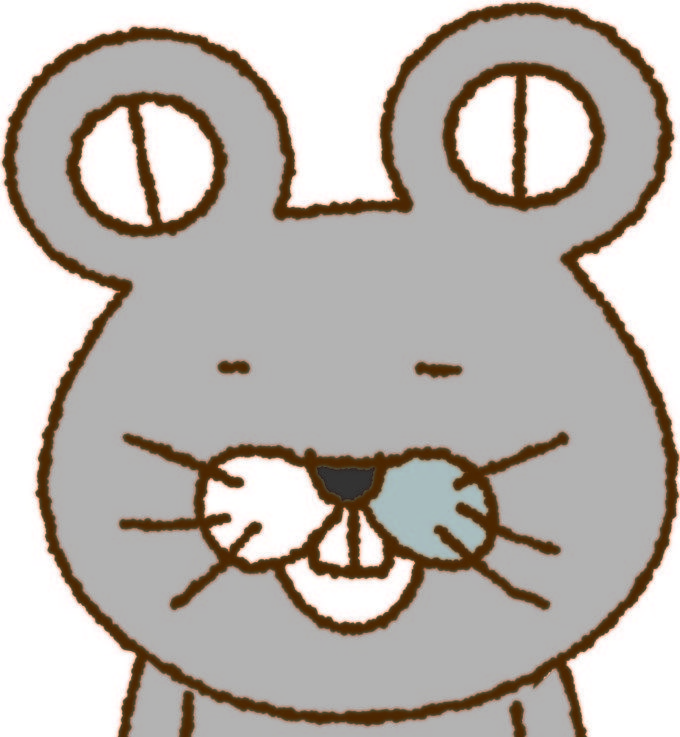
軽くホラーよな…
ワンダーデバイスで、私が一番気に入った点でもあります。
この遊び心は他の家じゃあ叶わない!

1つだけ改善点を上げるとすれば、階段からロフトにかけての手摺り部分には、誤って上から物を落とさないように、ネットもしくは板を取り付けるという対策が必要なんじゃないかと…。
小さい子供がいると、細かいおもちゃが散乱しますからね。

私、考えすぎ?
ワンダーデバイスの2階の個室は2つです。
ちょっと広いこちらは、主寝室になるのでしょうか。
狭い方にはベッドと机が置いてありました。
木目の壁が柔らかい雰囲気を出しています。
方角的には北側に位置する造りですが、まったく暗さや肌寒さを感じさせません。
ちなみに2階にトイレはなく、取り付ける場合はアレンジプランを採用することになります。
ワンダーデバイスの収納は申し分なし?
最後に、ワンダーデバイスの収納力はどうなのか?
玄関口とキッチン横に広めの収納と、2階にはそれぞれの部屋にクローゼットが、そして、ロフトの横にも広い収納がありました。

来客用のお布団などは、2階のロフト横の収納にしまうのがベストかな。
 BESSの家の収納は充実しているのか?という疑問
BESSの家の収納は充実しているのか?という疑問
ワンダーデバイスの値段はいくらくらい?
子供たちの心を鷲づかみにしたワンダーデバイスですが、お値段はいくらくらいなんでしょう?

ドキドキする…。
なんと、税込で…。
21,680,000円!!!
だよね~。このくらいはするよね~。
分かってた、分かってた。
「程々の家」や「カントリーログ」の標準価格を見てしまったせいで一瞬、
「あれ?安い??」
と思ってしまいがちですが、一度頭をリセットすると、まあまあそれなりのお値段。
でも、ワンデバかっこいいなぁ…。
私たち家族がワンデバ顔なら絶対にワンデバを選ぶのですが…。
どう頑張ってもワンデバとはかけ離れている(^^;)
んんん~。
早くどの家にするか決めなくちゃいけないのに、どの家も良すぎて選べません。
どうしたものか。
次回は「BESS仙台ログウェイ見学体験記」の最終回。
ワンダーボイドの見学の様子を書いていきたいと思います。
ここまでお付き合いくださった皆さま、ありがとうございました。
それでは!
合わせてどうぞ!↓↓
 BESSのログハウス『G-LOG(Gログ)なつ』見学体験記
BESSのログハウス『G-LOG(Gログ)なつ』見学体験記
 BESSの家を見学してきました。失敗しない家造りを目指して
BESSの家を見学してきました。失敗しない家造りを目指して
 倭様【程々の家】八風を見学してきた感想を包み隠さず書いてみる
倭様【程々の家】八風を見学してきた感想を包み隠さず書いてみる
 住宅ローンの返済って大変そう。失敗したくないのでFPさんに相談してみた
住宅ローンの返済って大変そう。失敗したくないのでFPさんに相談してみた










